更新日: 16/08/01
社友のお便り
社友会のみなさんから寄せられたお便りや随想などを掲載しています。ご自身の活動や、身の回りの出来事、読書の感想、人生の生き方など気軽にご投稿ください。
(画像の上のカーソルが ![]() になると拡大できます)
になると拡大できます)
ビートルマニア
市村 雅博
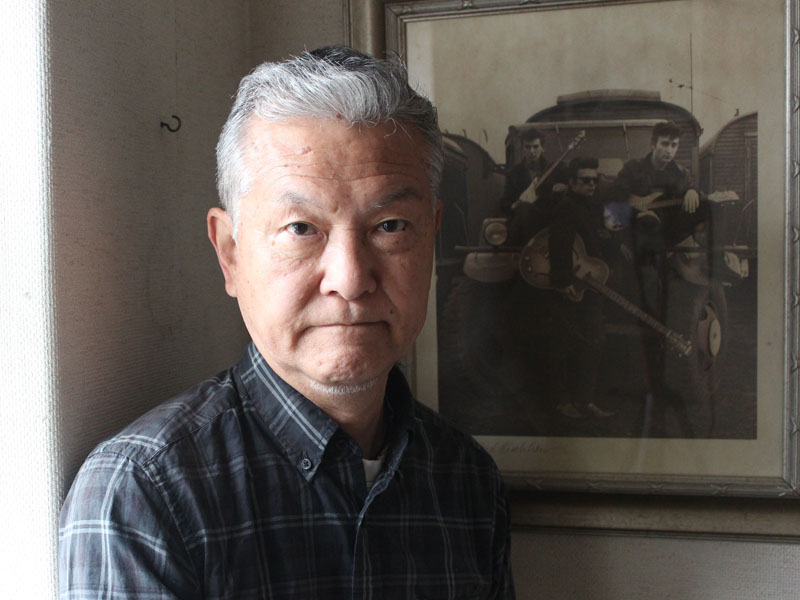 筆者近影
筆者近影英国リバプール出身の4人組ロックバンド、「ザ・ビートルズ」の熱狂的なファンのことを「ビートルマニア」と呼ぶ。かく言う私も、その「ビートルマニア」のはしくれである。私がビートルズの曲を初めて聴いたのは、彼らにとってデビュー2年目の1963年、私が中学2年生の時だった。正確に言うと、ビートルズそのものではなく、テレビの歌番組で、初代「ジャニーズ」(註1)が日本語で歌った「シー・ラヴズ・ユー」を聴いたのが最初だった。なぜか言葉では言い表せないような衝撃を受け、それが英国のビートルズというバンドの曲であることを知ると、ラジオのベストテン番組で彼らを追い駆けるようになり、すぐに直径17センチ45回転のEP盤や33回転のコンパクト盤を購入(当時のお小遣いでは、直径30センチ33回転のLPまでなかなか手が出なかった)、ビートルズ音楽の虜になるのにさしたる時間は掛からなかった。以来、かれこれ半世紀を超えるビートルマニア歴ということになる。
ビートルズの楽曲は、その多くが、ジョン・レノンとポ-ル・マッカートニーの共作曲(一般に、レノン=マッカートニーのクレジットを使用)を含め、ほとんどがメンバーの作詞・作曲によるオリジナルであることが最大の魅力であり、その独創的なメロディやコード進行とともに、絶妙なハーモニーが生み出す斬新な世界観が何とも言えず新鮮である。さらに言えば、初期の頃、マッシュルーム・カットと呼ばれたヘア・スタイルや襟なしジャケットの着用など、次々とユニークなファッションを生み出したことに見られるように、既成の概念に囚われない、新しい若者文化の牽引役を担ったことも魅力のひとつだ。そして何よりも、彼らは録音技術の面で、初期の多重録音や2トラックから4トラック、8トラックへと進む果敢な挑戦など、ポピュラー音楽界における先進的な変革者でもあった。
1965年、米国のテレビ番組「エド・サリバン・ショー」が日本でも放映され、その中でビートルズの出演シーンが流れた。当日は、番組の最初から最後まで、テレビに噛り付いていたことは言うまでもない。残念ながら、当時はビデオ・デッキも一般化しておらず、一夜限りの貴重なお楽しみであった。
1966年6月末、ビートルズが来日、日本武道館で公演を行った。当然のことながら、チケットを買って本物を観に行きたかった。しかし、父親に止められ、その夢は叶わなかった。当時、ビートルズの公演は熱狂的なファンで大混乱となる恐れがあり、怪我人も出かねないとマスコミが大々的に報道していたからだ。やむを得ず、7月1日夜のテレビ放映(同日昼公演の録画)で我慢したが、この世紀のイベントの現場に立ち会えなかったことは、私の人生にとって今でも心に残る一大痛恨事である。テレビで観た彼らの演奏は、曲目が僅か11曲と少なく、マイク・スタンドの不調などもあり、コンサートとしては不満の残る内容だったが、実際の演奏シーンを観られるチャンスなど、めったになかったので、テレビ鑑賞でもそれはそれで十分に楽しめた。ちなみに、彼らが宿泊した「東京ヒルトンホテル(現・キャピトル東急ホテル)」は、私が通っていた高校から至近距離にあり、警官隊による厳重警戒でホテルに近づくことも出来なかったのだが、昼休みなど、ドキドキと胸が躍る気分だったことを覚えている。
ビートルズは、あっと言う間に世界の音楽シーンを席巻したが、残念ながら、1969年1月頃からメンバー間の不和が伝えられ、1970年4月には解散してしまった。その後、ジョンは、ニューヨークに移り、独自の音楽活動を始めたが、ファンとしては、ビートルズの再結成を期待して止まなかった。その期待を脆くも打ち砕いたのが、1980年12月8日に起こった、熱狂的なファンによるジョンの射殺事件だった。当時、私はニューヨークに赴任して1年ほど経った頃であり、マンハッタンで取引先と会食中だったが、事件が臨時ニュースで報じられ、大きなショックを受けた。次の週末、事件現場のダコタ・ハウス(註2)の前に行き、小雪の舞う中で多くのファンとともに、ジョンの不慮の死を悼み、事件を嘆き悲しんだ。


